クラウドホスティングとは?種類・メリット・ツールの選び方を解説

クラウドホスティングは、ビジネスの成長に応じてリソースを柔軟に拡張できる、セキュリティと安定性に優れたWebサイト運用基盤です。
本記事では、クラウドホスティングの概念や、ほかのサーバー環境との違い、メリット、選び方について解説しています。
クラウドホスティングの導入を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
- クラウドホスティングとは
- クラウドホスティングの活用シーン
- クラウドホスティングを選ぶ際のポイント
- クラウドホスティングとは?
- レンタルサーバーとの違い
- オンプレミスサーバーとの違い
- VPSとの違い
- クラウドホスティングの種類
- パブリッククラウド
- プライベートクラウド
- マルチクラウドホスティング
- クラウドホスティングのメリット
- スケーラビリティが高い
- 柔軟にカスタマイズできる
- 大規模なサービスに対応できる
- 低コストで運用できる
- クラウドホスティングの選び方
- 利用したい機能があるか
- 予算内に収まるか
- サポートが充実しているか
- まとめ
クラウドホスティングとは?
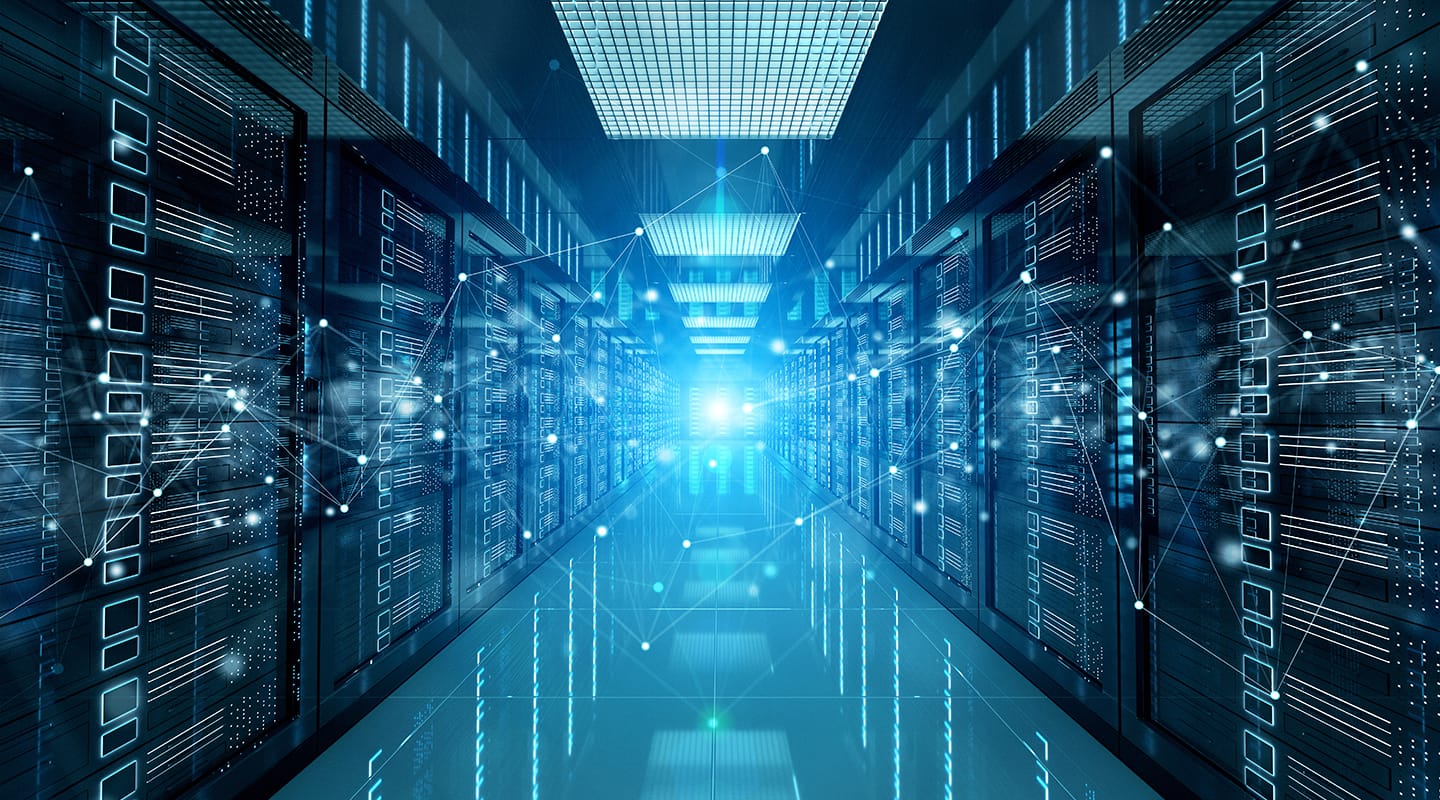
クラウドホスティングとは、インターネット経由で提供される仮想サーバー環境の一種で、必要なときに必要なリソース(CPU・メモリ・ストレージなど)を即座に割り当てられるホスティング形態です。
物理的なサーバーを所有する必要がなく、スケーラビリティやコスト効率に優れているため、企業のWebサービスや業務システムのインフラとして広く採用されています。
レンタルサーバーとの違い
クラウドホスティングとレンタルサーバーの大きな違いは、サーバーリソースの柔軟性にあります。
| 項目 | クラウドホスティング | レンタルサーバー(共用) |
|---|---|---|
| リソース | 柔軟に変更可能(スケーラビリティに優れる) | 固定プラン(変更には手間がかかる場合あり) |
| 料金体系 | 従量課金制が主流 | 定額制(月額・年額) |
| 得意な用途 | アクセス変動のあるサイトや拡張性を求めるサービス | 小規模サイトやブログ、メールの利用 |
クラウドホスティングでは、巨大なインターネット上のリソースから、必要な分だけオンデマンドで割り当てられます。アクセスが急増した場合には自動的にリソースが拡張され、トラフィックが落ち着くと元の状態に戻るといった、動的なスケーラビリティを実現できることが特徴です。
対して、共用レンタルサーバーは、あらかじめ決まった性能・容量に基づいた固定プランで提供されるのが一般的です。契約内容の範囲外の利用には制限があり、急激なトラフィックの増加には十分対応しきれないケースも少なくありません。
たとえば、オンラインストアがセールをおこなう際、クラウドホスティングならサーバーの負荷が自動調整され、表示遅延やダウンを防ぐことが可能です。一方で共用サーバーでは、処理が追いつかずページの表示が不安定になるおそれがあります。
つまり、アクセス量の変動が大きい、または今後の拡張を視野に入れている企業にはクラウドホスティングが適しているといえるでしょう。予算を一定に抑え、小規模で運用したい場合には、レンタルサーバーが無理のない選択肢になります。
オンプレミスサーバーとの違い
オンプレミスサーバーは、自社の設備としてサーバー機器を購入・設置・運用する方式です。これに対して、クラウドホスティングでは、サービス事業者が提供するインフラをインターネット経由で利用します。
この違いにより、クラウド型は初期投資を抑えられるうえ、サーバールームの確保や冷却・電源管理といった物理的な保守も不要になります。維持コストや人的リソースの削減に貢献するのが大きなポイントです。
オンプレミスは構成の自由度が高く、社内にすべてを置くことで完全なコントロールが可能です。しかし、導入には高額な機器費用や設置・構築の時間が必要であり、運用には専門知識を持つ人材も求められます。
スピードや柔軟性、コスト効率を重視するのであれば、クラウドホスティングが理想的です。セキュリティや法的な理由で外部環境を使えないケースでは、オンプレミスが有力な選択肢となります。
VPSとの違い
VPS(Virtual Private Server)は、1台の物理サーバーを仮想的に分割して提供するサービスで、各ユーザーが独立して利用できます。root権限が与えられるため、自由なカスタマイズが可能です。
| 項目 | クラウドホスティング | VPS |
|---|---|---|
| リソース拡張性 | 高い(動的なスケーリングに対応) | プラン内で固定(手動による変更が必要) |
| 料金体系 | 従量課金制が主流 | 定額制(月額・年額) |
| 管理者権限 | あり | あり |
| 自由度 | 非常に高い | 高い |
VPSでは契約時に決めたCPUやメモリなどのリソースが基本的に固定されており、アクセスが急増しても自動で拡張されることはないため、急激な負荷には対応しづらいという課題があります。
これに対し、クラウドホスティング(とくにIaaS)は、複数の巨大なサーバー資源から必要な分だけをリアルタイムに利用できる構造です。アクセス状況に応じてリソースの自動拡張(オートスケーリング)も可能であり、急激な負荷変動にも強い対応力を発揮します。
料金体系にも違いがあり、VPSは月額固定制が主流ですが、クラウドホスティングでは使った分だけ支払う「従量課金制」が一般的です。短期間の利用や予測できないアクセスがあるケースでは、クラウドの方が効率的に運用できます。
クラウドホスティングの種類

提供される仕組みや利用目的に応じて、クラウドホスティングはおもに以下のように分類されます。
- パブリッククラウド
- プライベートクラウド
- マルチクラウドホスティング
クラウドホスティングの種類ごとに特徴について、以下よりくわしく解説していきます。
パブリッククラウド
パブリッククラウドは、複数のユーザーが共通のインフラを利用する形式のクラウドホスティングです。インターネット経由で手軽にアクセスでき、初期費用が抑えられることから、導入のしやすさが大きな魅力です。
パブリッククラウドを提供しているクラウドベンダーは、自社で運用する大規模なデータセンターを活用し、安定性や拡張性に優れたサービスを展開しています。そのため、利用者は必要なリソースを迅速に確保でき、ビジネスのスピードに対応しやすくなります。
AI開発やビッグデータ解析などの高度な機能も提供されており、専門知識がなくても、画面操作(GUI)中心で簡単にサービスを開始できる点も強みです。たとえば、中小企業が新規のWebサービスを立ち上げる場合でも、月額数千円程度からスタートすることが可能です。
また、アクセスの増加に応じて自動でリソースを拡張したり、複数のサーバーを立ち上げたりすることも管理画面から簡単にできます。一方で、共用環境であるため、医療・金融などの高度なセキュリティ要件がある業種では、制約や導入の難しさが生じる場合があります。
プライベートクラウド
プライベートクラウドは、特定の企業または組織だけが専有するクラウド環境です。ほかの利用者とインフラを共有しないため、セキュリティ性が高く、システムの自由度も大きいのが特徴といえるでしょう。
たとえば、厳格なセキュリティ要件を課された業界や、既存の基幹システムとの連携が不可欠な場合には、プライベートクラウドが選ばれる傾向があります。外部の影響を受けにくいため、運用の安定性も期待できます。
プライベートクラウドの構築方法には、オンプレミス型とホスティング型の2つがあり、それぞれに特徴があります(以下の表を参照)。前者は自社内に物理サーバーを設置する方法で、後者はデータセンター事業者の設備を活用するモデルです。
| 項目 | オンプレミス型 | ホスティング型 |
|---|---|---|
| 特徴 | 自社設備内に構築 | 外部データセンターを活用 |
| 料金体系 | 従量課金制が主流 | 定額制(月額・年額) |
| メリット | 最大限のカスタマイズが可能で、物理的な制御も自社でできる | 物理管理の負担を軽減できる |
| デメリット | 初期費用が高く、運用負担が大きい | オンプレミスよりカスタマイズの自由度がやや制限されることがある |
金融機関や官公庁など、極めて高いセキュリティ水準が求められる組織では、プライベートクラウドの導入がスタンダードになっています。カスタマイズ性の高さも魅力ですが、導入・維持コストが高くなる傾向がある点には注意が必要です。
プライベートクラウドについては、以下の記事でくわしく解説しています。
マルチクラウドホスティング
マルチクラウドホスティングは、複数のクラウドサービスを併用する戦略で、特定のベンダーに依存しない柔軟な運用を可能にします。
この方法を採用すれば、クラウドベンダーごとの得意分野を組み合わせて活用できるだけでなく、特定のクラウドベンダーに依存する「ベンダーロックイン」のリスクも回避できます。障害発生時の冗長化にも有効です。
ただし、複数のクラウドを一元的に管理する必要があるため、構成は複雑になりがちです。セキュリティポリシーの整合やコストの最適化など、運用には高度な知識と体制が求められるため、導入には慎重な検討が必要です。
クラウドホスティングのメリット

クラウドホスティングを導入することで得られるおもなメリットを、 4つの視点から紹介します。
- スケーラビリティが高い
- 柔軟にカスタマイズできる
- 大規模なサービスに対応できる
- 低コストで運用できる
スケーラビリティが高い
クラウドホスティングが持つ特徴のひとつは、アクセスの増減に応じてサーバー性能を柔軟に調整できる点にあります。これは一般に「スケーラビリティが高い」と表現される特徴であり、ビジネス成長に追従できる強力な機能です。
クラウドでは、仮想化されたリソース群から必要な分だけを動的に割り当てることが可能で、CPUやメモリ、ストレージなどをリアルタイムで増減できます。物理的な機器変更を伴わず、管理画面上の操作のみで対応できるのも利点です。
たとえば、大型キャンペーンやメディア露出によってアクセスが急増した場合でも、クラウドならスケールアップ・スケールアウトでリソースを即時拡張できます。これにより、サービス停止を防ぎ、機会損失を最小限に抑えられます。
アクセスが落ち着いたタイミングでスケールダウンすれば、リソースを自動的に縮小することも可能です。このような調整により、過剰なコストを避けることができ、結果としてコスト最適化にも貢献します。
アクセス変動の激しいECサイトや、新興企業のWebサービスなどにはとくに向いており、柔軟な運用と費用対効果の両立が求められる現場で力を発揮します。
柔軟にカスタマイズできる
IaaSや一部のPaaS型クラウドホスティングでは、OSの選択からミドルウェア構成、ネットワーク設定まで、幅広いカスタマイズが可能です。こうした自由度の高さは、従来の共用レンタルサーバーと大きく異なる点です。
仮想サーバーに管理者権限(rootやAdministratorなど)を持てるため、必要なソフトウェアのインストールや設定変更が柔軟にできます。システム開発ポリシーに応じて細部までチューニングできるのも大きな強みです。
たとえば、特定バージョンのプログラミング言語やデータベース、Webサーバーを選定し、自社独自の環境構築をおこなうことも簡単に実現できます。
また、セキュリティの観点でも、独自のファイアウォールルールやアクセス制御を実装することで、より高度な防御体制を構築することが可能です。
ただし、自由度が高いということは、設計や運用に一定の知識・スキルが求められることを意味します。担当者のリテラシーや体制面にも配慮が必要です。
大規模なサービスに対応できる
クラウドホスティングは、大量のトラフィックや膨大なデータ処理を必要とするサービスにも十分対応可能です。これは、クラウド事業者が持つ巨大なインフラリソースと、多彩な補助機能によって支えられています。
大手のベンダーは、世界中にデータセンターを分散配置し、冗長性と可用性を担保しています。リージョンやアベイラビリティゾーンを活用することで、障害に強い構成を実現することが可能です。
さらに、ロードバランサーやCDN、高速なマネージドDBサービスなども整備されており、要求の高いアプリケーションでも安定稼働が可能です。こうした機能を組み合わせれば、グローバルスケールでの展開も視野に入ります。
大手SNSや動画配信サービスの多くも、こうしたクラウド基盤を採用しており、実績面でも信頼性が証明されています。仮に同等の環境をオンプレミスで構築する場合、膨大な設備投資と専門知識が不可欠です。
その点、クラウドなら初期費用を抑えつつ、段階的なスケールに対応できる柔軟性が大きな武器になります。
低コストで運用できる
クラウドホスティングでは、多くの場合従量課金制が採用されており、実際に使った分だけ料金が発生します。これは、初期費用が限られる中小企業やスタートアップにとって大きな利点です。
物理サーバーの購入・設置といった初期投資が不要なため、導入のハードルが下がります。オンプレミスと比べて数十万〜数百万円単位の費用を削減できるケースも珍しくありません。
また、CPU使用率・データ転送量・ストレージ使用量などをベースにした課金体系により、リソース消費を抑えることで運用コストも効率化できます。
たとえば、サービスの開発初期は低スペック構成で費用を最小限にし、トラフィックの増加に応じてリソースを段階的に拡張する運用が可能です。
ただし、従量課金には注意も必要です。リソース管理が甘いと、意図せず高額な請求が発生することもあります。モニタリングや自動停止設定などを活用し、つねに使用状況を把握することが重要です。
クラウドホスティングの選び方

クラウドホスティングを選ぶ際のポイントは、以下のとおりです。
- 必要な機能が揃っているか
- 予算に収まるかどうか
- サポート体制が整っているか
利用したい機能があるか
まず確認すべきは、自社で構築したいWebサイトやアプリケーションに必要な機能が、そのクラウドサービス上で利用可能かどうかです。提供される機能や環境はベンダーやプランによって大きく異なります。
たとえば、OS(Windows ServerやLinux系)や開発言語(PHP、Java、Pythonなど)、データベースの種類(MySQL、PostgreSQL、NoSQLなど)など、基盤となる技術要素がサポートされているかをチェックしましょう。プランによっては、それらの自由なインストールが制限される場合もあります。
WordPressを使いたい場合は、PHPとMySQLが使える環境であることが前提条件になります。また、CDNやWAF、自動バックアップ、ロードバランサーといった機能が標準搭載されているか、あるいは有料オプションかどうかも見落とせません。
必要な機能が提供されていない場合、システムが正常に動作せず、再構築や移行といった手間が発生するおそれがあります。そのため、まずは必要な要件をリストアップし、各クラウドの仕様書と突き合わせて検証しましょう。
可能であれば、無料トライアルを活用し、管理画面の使いやすさや操作感を体験しておくと安心です。
予算内に収まるか
クラウドホスティングの料金体系は多くの場合、従量課金制が基本です。使用量に応じてコストが変動するため、事前に月々の想定費用を試算しておくことが大切になります。
CPU使用量やストレージ容量だけでなく、データ転送量やストレージ、オプション機能なども課金対象となる場合があります。細かな費用項目まで把握しておかないと、予想外のコストが発生する可能性があるため、十分な注意が必要です。
とくに画像や動画が多いサービスでは、転送コストが想定を超えて膨らむケースが多く見られます。安価なプランに見えても、データ転送量だけで月額数万円に達するケースも実際にあります。
料金シミュレーターや試算ツールを使って、自社の利用シナリオをもとにコストを把握しておくことをおすすめします。基本料金に加え、サポートやライセンス料などの隠れたコストも見逃さないようにしましょう。
料金の安さだけでなく、課金単位やアラート機能の有無、データ転送料の上限なども含めて総合的に判断する姿勢が求められます。
サポートが充実しているか
クラウドに関する知識が不足している場合や、インフラ専任者がいない企業では、サポート体制の充実度がサービス選びのカギになります。万が一のトラブル時に、どれだけ速やかに解決に導いてもらえるかは重要です。
サービスの特性上、設定ミスや予期せぬ障害、セキュリティの問題など、さまざまなトラブルが発生する可能性があります。それらに迅速に対応できるサポートがあれば、ビジネスへの影響も最小限に抑えられるでしょう。
確認すべき点としては、対応時間(24時間365日対応か)、問い合わせ方法(電話・メール・チャット)、回答の目安時間、SLAの有無などが挙げられます。
また、操作案内やテクニカルサポートといった問い合わせ対応がどこまで可能か、日本語でのサポートを提供しているかなどもチェックしておきましょう。
多くのベンダーでは、無料で利用できる基本的なサポートと、専門的な対応が含まれる有料サポートプランの両方を提供しています。自社のスキルレベルや、求める稼働率に応じて最適なサポートを選択してください。
加えて、SLAで定められた稼働率や、それを下回った際の補償内容も事前に確認しておくと安心です。導入事例や口コミ、レビューサイトなども参考にしながら、信頼できるサポート体制を持つクラウドベンダーを選びましょう。
まとめ
クラウドホスティングとは、インターネット経由で提供される仮想サーバー環境の一種です。物理的なサーバーを所有する必要がなく、スケーラビリティの高さや、カスタマイズの柔軟性がメリットです。
クラウドホスティングを選ぶ際は、構築したいWebサイトやアプリケーションに必要な機能が備わっているか確認してください。また、予算内に収まるか、サポート体制が充実しているかチェックしましょう。
さくらのクラウドを活用することで、安心・高性能なクラウド環境を実現できます。国内データセンターによる高速・安定した接続、柔軟なスケーリングが魅力です。下記の資料をダウンロードして詳細をご確認ください。





